
USCPA(米国公認会計士)の合格までにどのくらいの勉強時間が必要か知りたい
このようなお悩みにお答えします。
今回の記事では、アビタスで勉強&Big4監査法人で働きながらUSCPA試験に合格した私の実際の勉強時間をご紹介したうえで
- 各科目の勉強時間
- 週単位での勉強時間
- 平日や土日単位での勉強時間
について解説していきます。
今回の記事を読んでいただければ、自分の合格までの勉強スケジュールを詳細に計画できるかと思いますので、興味のある方は是非読み進めてみてください。
忙しい社会人・学生でも合格できる!おすすめのUSCPA予備校3選はこちら
- アビタス |【圧倒的合格実績】日本人USCPA合格者の約3人に2人が選ぶ王道予備校
- CPA会計学院|【業界最安】超格安で始められる注目スクール
- 資格の学校TAC<USCPA(米国公認会計士)>各種コース開講 |【教材の質に定評】ハイクオリティな講座&より確実な合格を求める受験生向け
私のUSCPA試験の勉強時間は1,450時間だった

まずは結論から。
私がUSCPA試験合格にかかった勉強時間は1,450時間でした。
ちなみに多くのブロガーやSNSアカウントを見る限り、1,500-2,500時間が合格までに必要な勉強時間。
1,450時間という私の勉強時間は、USCPA受験生としては比較的平均的な勉強時間と言えます。
早い人は500~600時間程度であっさり合格する方もいます。
しかし、これはかなりの少数派。
大半の人はやはり1,000時間以上はかかることを覚悟した方がいいかもしれません。
USCPA試験の勉強時間の推移
USCPA試験の勉強時間について、どのような時系列で合格したのかについてもう少し深掘りします。
まず、USCPA試験を勉強する前の私のスペックは以下のとおりです。
- 簿記2級取得済み
- TOEICスコア700点台
- 事業会社経験はあるが経理経験なし
- 未経験・無資格で監査法人へ転職
勉強面では簿記スキルも英語スキルもそこそこ、といった状況です。
しかし、「売掛金=Accounts Receivable」など瞬時に浮かぶはずもなく、英語で会計の専門知識を学ぶにはド素人の状態でした。
さらに経理経験はまったくのゼロ、監査もアシスタントの立場で始めたばかりで実務経験も乏しい状況でした。
勉強開始時点では、USCPA受験に必要なスキルはほぼ持っておらず、初心者レベルでした。
科目別の勉強時間は以下のとおりです。
FAR:500時間
AUD:300時間
BAR(当時はBEC):250時間
REG:400時間
合計:1,450時間
また、私がアビタスに講座を申し込んでUSCPAの勉強を開始してから、実際に全科目合格までに至ったスケジュールは以下のとおりです。
- 2020年1月~3月:英文会計入門・会計学の単位取得
- 2020年4月~8月:仕事に慣れるため勉強中断
- 2020年9月~11月:FAR1回目250時間(スコア63で不合格)
- 2020年12月~2月:AUD1回目200時間(スコア74で不合格)
- 2021年2月~3月:BAR1回目150時間(スコア73で不合格)
- 2021年4月~5月:AUD2回目100時間(スコア75で合格)→1科目合格
- 2021年5月~7月:FAR2回目250時間(スコア86で合格)→2科目合格
- 2021年8月~9月:REG1回目250時間(スコア66で不合格)
- 2021年9月~10月:BAR2回目100時間(スコア79で合格)→3科目合格
- 2021年11月~12月:REG2回目150時間(スコア75で合格)→4科目合格
アビタスへ入会したのは2020年1月でしたが、本格的にFARの勉強を開始したのは2020年9月頃です。
4科目合格までに要した期間としては16ヶ月(2020年9月~2021年12月)となります。
またご覧のとおり、私は4科目すべて2回目の受験で合格しています。
しかし、きちんと勉強すればすべて1発合格も可能ですし、逆に3回以上受験する方もたくさんいらっしゃいます。
私や知人の合格者の情報を総合的に踏まえると、多くの合格者が「1~2科目は初回受験で落としている」といった印象です。
そのため、平均的なUSCPA受験回数は「8回前後」と思われます。
あくまで上記は一個人の勉強記録にすぎませんが、私の勉強時間をもとに各科目の目安となる勉強時間を逆算していきます。
USCPA科目①FARの勉強時間:約400~600時間

FARで私がかかった勉強時間は約500時間です。
受験1回目・2回目ともに250時間程度を費やしました。
FARを始める前は、アビタスの英文会計入門で会計学の単位を取得しました。
しかし最初の受験科目ということもあり、どこまでやれば合格ラインが分からないまま本番に突入し、スコア63で玉砕しました。
1回目の受験ではMC2周、TBSを1.5周程度回しましたが、全然演習が足りなかったな…という印象です。
また、
- 受験直前までリリース問題(AICPAからアビタスに提供され、アビタスのサイトのみで閲覧できる本番レベルの問題)を知らなかった
- リサーチ問題の解き方をいまいちつかめなかった
- 模擬試験の復習をしなかった
- 本番での時間配分に合わせた演習を模試以外でしなかった
など、複数の要因が重なったことで不合格となったのだと思います。
2回目の受験では、上記の失敗経験を踏まえ、
- 追加でMC3周・TBS2周
- 基本の仕訳を繰り返し書いて暗記
- 各単元ごとに論点をまとめる
- 過去6~7年分のリリース問題を2周
といった演習により、スコア86で合格しました。
2回目に関しては既にインプットは終わっていたので、本番を想定したアウトプットに時間を割くことができました。
USCPA科目②AUDの勉強時間:約250~400時間

AUDで私がかかった勉強時間は約300時間です。
内訳としては、受験1回目で200時間、2回目で100時間程度です。
2科目めとしてAUDの勉強を開始した頃は、既に監査法人での期末の繁忙期を経験し、監査の内容も実務で理解を進めていました。
そのため、「早く受からなければ!」という焦りから、FARの合格発表を待たずに勉強を進めました。
FARの時にうまくできなかった経験を踏まえてMC・TBSとも3週前後、リリース問題も2周程度しましたが、結果は1点差で不合格でした。
敗因としては、テキストの読み込みや暗記が不足していたことがあると思います。
ちなみに、スケジュール上ではFAR→AUD→BEC→AUD(2回目)という順番で受験しています。
なぜFAR2回目ではなくAUD2回目を先に受験したか?ですが、
- AUD1回目はスコア74で落ち、もう少し勉強すれば合格点に到達できるだろうと予想していた
- AUD2回目の受験時期が監査法人の繁忙期(4月~5月)であり、腰を据えてFAR受験はできないと考えた
といった戦略があったからです。
また、AUD2回目の時点で3科目連続不合格の状態で、精神的にもかなり厳しく「自分はずっと合格できないのでは…」という不安と闘う日々でした。
結果的に2回目はギリギリのスコア75での合格でしたが、負のサイクルから抜け出し繁忙期直後に合格でき、自分にとって大きな自信となりました。
USCPA科目③BARの勉強時間:約250~450時間

BAR(当時はBEC)で私がかかった勉強時間は約250時間です。
※2021年に私が受験した頃はBECという科目でしたが、2024年以降は3つの選択科目から1つを選べば良い形式に変わり、その中ではBARという科目に最も近いのではないかと思われます。
内訳としては、受験1回目で150時間、2回目で100時間程度です。
FAR1回目の不合格を知り、AUD1回目についても不合格通知を受けた最中でのBECのチャレンジは、精神的に厳しいものがありました。
しかし、これも焦りから、追い打ちをかけるように1回目の受験もスコア73で不合格となります。
このときは、MC・TBSともに1.5周、WC(ライティング)20問程度を解いたのみで(当時はライティング形式の問題もありました)、リリース問題にもまともに手を付けていないひどい状態でした。
その後、2回目のチャレンジでは
- MC・TBS:いずれも2周
- WC:アビタスの巻末にある100題超の1問1答を自分の言葉で作成
- リリース問題:直近3年を2周
といった演習により、スコア79で合格できました。
USCPA科目④REGの勉強時間:約350~500時間
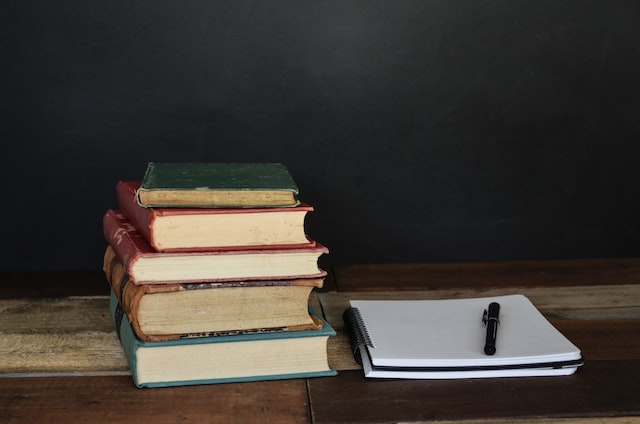
REGで私がかかった勉強時間は約400時間です。
内訳としては、受験1回目で250時間、2回目で150時間程度です。
4科目めの科目なので、REG開始直後は「勉強を進めるうちに合格できそうか分かるだろう」と高をくくっていました。
しかし、実際に学習を始めてみると、MC・TBSをこなしてもREGの実力がついている実感が薄かったです。
結果として、受験1回目はスコア66で不合格、2回目もコンスタントに勉強したところスコア75でのギリギリ合格となりました。
2回目の受験直後も自信がなく「3回目もあるかな…」と思っていた矢先の合格通知だったので、REGは唯一、自分の感触と結果が一致しない科目でした。
USCPA試験の勉強時間(合計):約1,250~1,950時間

私がかかった4科目合計の勉強時間は約1,450時間、期間にして実質16ヶ月です。
勉強時間としては、概ね平均的な実績かと思われます。
冒頭でもチラッとご紹介しましたが、アビタスをはじめとするUSCPA予備校では「USCPA試験は最短1,000時間で合格できる」と謳われています。
この数字は100%間違いではありませんが、極めて実現可能性が低い勉強時間だと思います。
なぜなら、
- 英語の基礎知識がすでに高い(スコア800以上~)
- 簿記1級や日本の会計士・税理士試験に合格している
といったハイスペックな方を想定しているからです。
「USCPAは簡単である」という意見を聞くのが残念ですが、英語・会計ともに初心者の場合、ハードルはかなり高い資格試験です。
よって、USCPA試験は余裕を見て「1,500時間前後の勉強時間を覚悟すべき試験」と考えています。
忙しい社会人・学生でも合格できる!おすすめのUSCPA予備校3選はこちら
- アビタス |【圧倒的合格実績】日本人USCPA合格者の約3人に2人が選ぶ王道予備校
- CPA会計学院|【業界最安】超格安で始められる注目スクール
- 資格の学校TAC<USCPA(米国公認会計士)>各種コース開講 |【教材の質に定評】ハイクオリティな講座&より確実な合格を求める受験生向け
USCPA試験の勉強時間のスケジュールは?

私自身、上記のUSCPAの勉強時間を費やす前は「全科目合格までに1~2年くらいかかるかな…」という漠然としたイメージを持っていました。
結果的に16か月(約1年半)と、ある程度自分の計画どおりに全科目合格できたと自負しています。
しかし、「できれば勉強時間を短縮して、すべて1発合格したかった」という悔しさもあります。
そして「もっとこうすれば効率的に合格できたかも」と思うのが、1週間・1日ごとにざっくりどのくらいの勉強時間を設けるか考えることです。
そこで私のUSCPA試験の勉強時間に基づいて、1週間単位・1日単位での必要な勉強時間をブレイクダウンしてみます。
勉強スケジュールとしては、ある程度余裕をみて「1年半(18か月)」での合格を見据えたシミュレーションをしていきます。
①1週間あたりのUSCPA試験勉強時間目安
1年間を50週とすると、1年半で約75週という想定です。
また、必要な勉強時間を1,500時間と仮定すると、
1,500時間/合計÷75週=20時間/1週間あたりの勉強時間
となります。
私も実際に働きながら勉強していた間は、毎週20~25時間を確保していましたので、目安の勉強時間としては妥当かと思います。
②1日あたりのUSCPA試験勉強時間(目安)
仮に毎週20時間の勉強時間を1日単位で割ると、
20時間/週÷7日≒3時間/1日あたりの勉強時間
となります。
ただし、私自身、毎日コンスタントに3時間を勉強できていたわけではありません。
時にはサボる日もありつつ、平日と土日でメリハリをつけて学習していたので、
平日の1日あたり平均勉強時間:1~2時間
土日の1日あたり平均勉強時間:5~6時間
といったペース配分です。
③各科目ごとのUSCPA勉強期間
実際の勉強時間をもとに、各4科目に充てるべき勉強期間をシミュレーションすると以下のとおりです。
FAR:500時間/合計÷3時間/1日あたりの勉強時間=166日(約5.5ヶ月)
AUD:300時間/合計÷3時間/1日あたりの勉強時間=100日(約3.3ヶ月)
BAR:250時間/合計÷3時間/1日あたりの勉強時間= 83日(約2.7ヶ月)
REG:400時間/合計÷3時間/1日あたりの勉強時間=133日(約4.4ヶ月)
ただし、私のBARにの実績については、科目が好きだったのと集中して勉強できる期間が長かったため、短期間で突破することができました。
なので実際のBARの勉強期間は、3ヶ月~3.5ヶ月ほどを見込むのが良いと思われます。
④短期突破を狙う場合のUSCPA勉強時間
もし「半年~1年で合格したい!」という方がいれば、単純にこの勉強時間を2倍にするイメージです。
平日の1日あたり平均勉強時間:3~4時間
土日の1日あたり平均勉強時間:10~12時間
くらいの時間を確保できるようであれば、半年間集中してチャレンジするのもアリです。
まとめ:USCPA(米国公認会計士)試験は勉強時間をしっかり確保して合格できる!

資格試験の勉強を始めるうえでは当たり前のことかもしれませんが、社会人でも大学生でも、トータルの勉強時間は同じです。
そのため、「自分はUSCPA全科目合格まで、どのくらいの期間を要するのか?」を逆算することは、受験対策上欠かせません。
USCPA受験生の多数が社会人で占められている印象ですが、社会人・大学生問わず、すべての方が丁寧に勉強スケジュールを立てるべきです。
- 半年で受かった!
- 2年以上かかった…
など、多くの意見が散見されるのがUSCPA試験の特徴ですが、結局は「1週間・1日のうち、どれくらいの勉強時間を投入できるか?」によって期間は異なります。
社会人の方でも週3~4日勤務や残業の全然ない方がいたり、大学生であっても、講義・バイト・サークルなどで多忙かもしれません。
重要なのは、「脳や体が疲弊していない」状態の時間を捻出して、いかに集中して学習を継続するか?ということです。
既にご紹介した、「週単位」「1日単位」での勉強時間の目安を踏まえて、自分は何時間捻出できるか?を考えてみてはいかがでしょうか。


