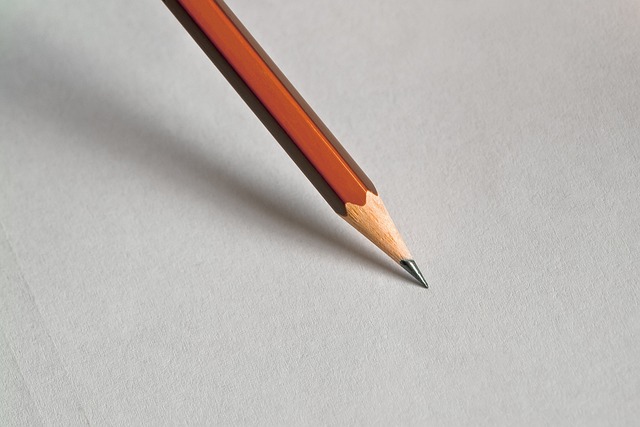
USCPAの新制度では、選択科目として「BAR(Business Analysis and Reporting)」という科目が登場しました。
名前だけ見るとピンと来ない方も多いかもしれませんが、実はこのBARは「数字を使って考える力」を問う実践的な内容になっており、将来のキャリアにも直結しやすい科目です。
この記事では、これからUSCPA試験を受ける方や、BARと他の選択科目(TCP・ISC)で迷っている方向けに、出題内容・勉強法・難易度・受けた方の感想や口コミ・おすすめタイプまで
今回の記事を読めばBARについて理解を深め流ことができ、あなたのUSCPA合格までの時間が短縮するのに役立つはずです。
それでは早速まいりましょう!
忙しい社会人・学生でも合格できる!おすすめのUSCPA予備校3選はこちら
- アビタス |【圧倒的合格実績】日本人USCPA合格者の約3人に2人が選ぶ王道予備校
- CPA会計学院|【業界最安】超格安で始められる注目スクール
- 資格の学校TAC<USCPA(米国公認会計士)>各種コース開講 |【教材の質に定評】ハイクオリティな講座&より確実な合格を求める受験生向け
USCPAの選択科目「BAR」とは?

2024年の試験制度改革(通称:CPA Evolution)により、USCPAは「Core科目3つ+Discipline科目1つ」の構成になりました。
- Core(必須):FAR/AUD/REG
- Discipline(選択):BAR/TCP/ISC
この中でBAR(Business Analysis and Reporting)はFARの延長線上にあるような科目で、財務データをどう読むか?どう報告・分析するか?という視点が問われます。
実務で言えば
- FP&A
- 経営企画
- 財務分析
- サステナビリティ報告
といった領域を想定した内容です。
「帳簿をつける」よりも「その数字をどう経営に活かすか」といったレベル感の問題が中心になっています。
特に近年は、財務報告だけでなく非財務情報の開示(例:ESGや統合報告)も重要視されているため、会計の知識をビジネス判断に結びつけられる人材が求められています。
そういった背景を考えると、BARはこれからのUSCPA像に合った選択科目とも言えます。
BARの出題範囲&形式は?

続けて、BARの出題範囲&形式についてご紹介します。
①BARの出題比率と3つのエリア構成
BARの出題範囲は、大きく以下の3分野に分かれています。
- Business Analysis:CVP分析(損益分岐点)、バランストスコアカード、原価管理、意思決定会計など (40〜50%)
- Technical Accounting:IFRS、連結会計、収益認識、無形資産、ヘッジ会計、セグメント情報など(35〜45%)
- Governmental Accounting:州・地方政府の会計、基金会計、GASB基準に基づく予算実績比較など (10〜20%)
財務会計の応用だけでなく、財務分析・政府会計まで幅広くカバーされており、FARで扱ったテーマが多く再登場するのが特徴です。
ただし、FARよりもどう使うか?どう伝えるか?といったビジネス視点が強く、単なる会計知識の暗記では太刀打ちできないのに注意が必要です。
②BARの試験形式と配点構成
他のUSCPA試験と同様、BARの試験時間は4時間です。
途中で15分の休憩(オプション)が設けられており、構成は以下のとおりです。
- MCQ(Multiple Choice Questions):2つのテストレット、合計50問
- TBS(Task-Based Simulations):3つのテストレット、合計7問(うち1問はリサーチ問題)
MCQは知識を問う問題に加え、実務的な判断を問う問題も混ざっており、単なる暗記型では対応が難しいこともあります。
一方のTBSでは財務諸表をもとにした比較・分析・意思決定の判断が求められます。
計算力よりも「資料を読み解く力」「適切な構造をつかむ力」が試されるため、英語の資料をどう効率よく読むか?が合否を分ける大きな要因となります。
特に後半のTBSが重めなので、本番で時間配分に失敗する受験者も多い印象です。
日頃からの練習問題・リリース問題・模試・直前対策といった学習を通じて、「資料を読む→要点を整理する→解答する」のリズムを体得しておくことが重要です。
③BARの時間配分&目安解答時間
BARの時間配分と1問あたりの目安解答時間は以下のとおりです。
No.1:40分/MC25問=約96秒/1問
No.2:40分/MC25問=約96秒/1問
No.3:45分/TBS 2問=約23分/1問
休憩:15分
No.4:70分/TBS 3問=約23分/1問
No.5:45分/TBS 2問=約23分/1問
BARのMCは25問とFAR並みに少ないので、比較的早く終わると思います。
傾向としてはFARと似ていますが、財務会計の上級の論点も出題されることから、あまり考えている時間が長すぎるとTBSを解くための時間が減って焦る可能性もあります。
USCPA試験全体の傾向として、後半のTBSにかけてバテる試験でもあるので、特にテストレット4・5あたりの解答時間に余裕をもたせておくことが重要だと思います。
BARの学習時間は?

BARは、一見するとFARの延長で「すでに勉強した内容が多いから楽なのでは?」と思われがちですが、実際に勉強を始めてみると予想より手ごわいと感じる人が多い科目です。
私の場合、2021年の受験当時はBECという受験科目でしたが、初回合格までに必要だった学習時間は以下のとおりです。
- 1回目:約150時間(不合格)
- 2回目:約100時間(合格)
→ 合計:約250時間
当初は「FARに似てるから少し軽めに見積もってもいけるだろう」と考えていましたが、分析問題やリサーチTBSで時間を使いすぎて撃沈しました。
2回目では、問題演習とTBSの読み込みのバランスを修正し、時間配分も徹底的に意識してようやく合格ラインに乗った、というのが正直なところです。
また、他の受験仲間に聞いても感じたのは、BARは人によって感じる難易度に差が出やすく、「得意な人にはサクサク進むが、苦手な人は沼にはまる」という性格の科目である点です。
一般的には200〜300時間の学習時間を見込んでおくと安心ですが
- TBS慣れしているか?
- 分析的な問題への抵抗がないか?
などでも大きく変わってくる印象です。
BARの勉強法のポイント:浅く広く重点は「分析」寄り
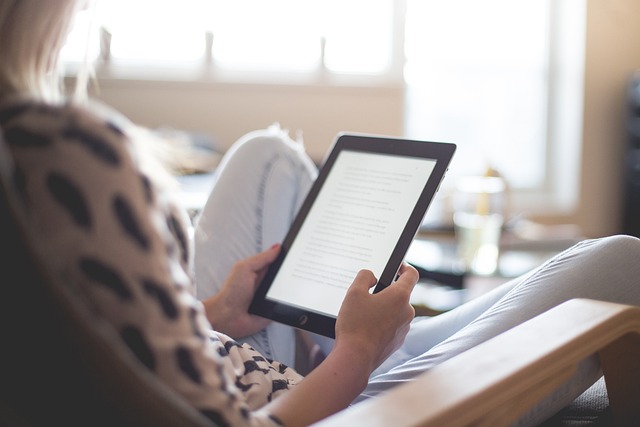
BARは範囲が広く、どこまで深掘りすべきか迷いやすい科目です。
全体像としては、FARの応用に「経営分析」の視点を加えたような構成です。
そのため完璧を目指すよりも、広く触れつつ頻出論点は繰り返して慣れる戦略が有効です。
私のBARの1回目・2回目の勉強内容をまとめると以下のとおりです。
1回目
・MC・TBSともに1.5周
・リリース問題:直近3年を1周
・サンプルテスト
2回目
・MC2周・TBS1.5周
・各論点のまとめ
・リリース問題:直近5年を2周
・サンプルテスト
私が行った勉強対策についてもう少し深掘りしてみます。
①MCとTBSをテーマごとに2〜3周する
特にMCQは「パターンで解けるか」よりも、「文脈から判断する力」が問われる問題が多いため、1周目は解けなくても気にせず、選択肢ごとの根拠を必ず確認することが大事です。
また、TBSは資料の量が多いので、1問を丁寧に読み込む練習をしましょう。
② AICPAリリース問題やサンプルテストを活用する
直前期の最大のポイントは、MC・TBSをバランスよく対策することだと思います。
特に本試験の形式・時間感覚に慣れるためには、リリース問題の活用が欠かせません。
具体的な対策としては、テキストを読みつつMC・TBSを2~3周回した段階で、早めにリリース問題に取り掛かるようにするのがいいです。
さらに「TBSのリサーチ問題」は独特なので、問題の探し方、根拠の読み方、英語での検索スキルなども含めて慣れておきましょう。
③ 要点ノートを作って反復復習
出題範囲が広いので、自分なりに「何が出やすいか」をメモしながら学習するのがおすすめです。
問題演習だけでは学習範囲を網羅するのには限界があり、論点を忘れることもあるので、自分の言葉でキーワード・重要論点整理する作業は非常に大切です。
例えば、セグメント情報・ヘッジ・意思決定会計などはTBSでも問われやすいため、図解や表でまとめておくと後々効いてきます。
とはいえ、ノートに何ページにもわたって論点を書き出す必要はありません。
私の場合は、テキストを丁寧に見直したうえで、テキストの裏表紙に自分の苦手ポイントや頻出ポイントを書き出すようにしました。
忙しい社会人・学生でも合格できる!おすすめのUSCPA予備校3選はこちら
- アビタス |【圧倒的合格実績】日本人USCPA合格者の約3人に2人が選ぶ王道予備校
- CPA会計学院|【業界最安】超格安で始められる注目スクール
- 資格の学校TAC<USCPA(米国公認会計士)>各種コース開講 |【教材の質に定評】ハイクオリティな講座&より確実な合格を求める受験生向け
BARの本番レベルの問題をチェック!

それでは、BARの本番レベルの問題を以下のとおり見てみましょう。
実際のレベルに触れることで、合格レベルの思考過程がイメージがしやすくなると思います。
①ビジネス分析のMCの例
例えば以下はMCのサンプルテストです。
ある部門の収益性を高めようとしているが、重要な機械の稼働能力が限られている。
この状況で、経営者にとって最も有用な意思決定手法はどれか?
①制約理論(ボトルネック・TOC)
②経済発注量(EOQ)
③バランスト・スコアカード(BSC)
④原価差異分析
正解は①です。
制約理論は、機械や人手が限られている状況において、「どのプロセスがボトルネック(障害)となって収益化が滞っているのか?」を把握・改善する理論です。
ちなみに合格ラインは、「稼働能力が…」といったキーワードを見た瞬間に、①を思い浮かべられるレベルになっていればOKと思われます。
そのためにも、テキストをみて、問題を解いて、間違えたらもう一度テキストを見て書き足して…という地道な作業はどうしても必要になります。
また計算以外にも、上記のような理論問題もバランスよく出題されるのがBARの特徴です。
「このキーワードが来たら、この選択肢を選べる」といった問題構成が多いという点で、AUDよりもFARやREGの理論問題に性質が似ている印象です。
合格レベルでは、ある程度の用語とその意味は暗記していることになるので、問題によっては選択肢をざっと読んでから問題を解く方が早いパターンもあります。
②公会計のMCの例
一方の公会計は、範囲も良くわからない、学習したことがない方がほとんどだと思います。
イメージしづらいと思うので、こちらも日本語訳したサンプルテストをご紹介します。
政府機関は、以下のどの財務諸表においてキャッシュフロー計算書を含めることが要求されているか?
①政府系ファンドの財務諸表
②政府全体の財務諸表
③企業会計区分財務諸表
④受託者ファンドの財務諸表
こちらの正解は「③企業会計区分財務諸表」となります。
問題を解くときの思考プロセスは以下のようなイメージです。
政府の財務報告の中でも、企業会計区分で作成される財務諸表は、一般的な事業会社寄りの報告が求められていたはず。
↓
通常、規模の大きい事業会社においては、キャッシュフロー計算書の作成が要求されてて、性格の似ている企業会計区分の政府機関も考え方は同様だったはず。
↓
他の選択肢だと、「政府」の性格が強い(「会社」っぽくない)ので、予算を決めた後のキャッシュフローより、そもそも予算をどう分配するかに重点を置いていたような…。
↓
だから、今回の出題では③が正解だろう。
上記のような思考プロセスを試験前までに身に付けたうえで、解答を導くこととなります。
問題によっては、上記のような1行のシンプルな問題もあれば、10行以上にわたる問題もありますので、本番はペース配分に注意して進める必要があります。
このように、公会計はあまり計算問題が出ない一方、大まかな理解を前提とした「暗記」がモノを言う領域となっています。
なお、上記のサンプル問題は政府会計からの出題ですが、NPO会計も重要な学習範囲となっています。
BAR vs 他の選択科目(TCP・ISC)の選び方

USCPAの選択科目は、BAR(Business Analysis and Reporting)の他に、
- TCP(Tax Compliance and Planning)
- ISC(Information Systems and Controls)
の2つがあります。
この中からどれを選ぶかは、自分の得意・不得意や本試験での相性を踏まえて慎重に考える必要があります。
①TCPとの違い
TCPは名前のとおり税務中心の科目で、個人・法人の税務申告や国際課税、税務プランニングなどが出題されます。
REG(税法)の延長のような側面が強く、「税金・ルール系が得意な人」や「実務で税務に関わる予定のある人」には相性の良い選択肢です。
ただし、タックス特有の言い回しや専門用語が多く出てくるため、暗記が苦手な人にはやや負担が重く感じられるかもしれません。
②ISCとの違い
ISCはIT・システム寄りの内容で、情報システム、内部統制、リスク管理、セキュリティ、IT監査といったトピックが中心になります。
監査や内部統制の知識と親和性が高く、文系SE、監査法人での内部統制経験がある人などに向いている選択科目です。
一方で、情報セキュリティやアクセス管理など、ITに馴染みがない人にとっては内容が抽象的に感じられることもあります。
③BARが向いている人
BARは「数字を読んで意味を考えるのが得意な人」に向いている選択科目です。
特に以下のような方にはおすすめです。
- FARで良い感触があった/会計が得意
- 経営企画やFP&Aなど、分析・レポーティング系のキャリアを考えている
- TBS形式の問題に抵抗がなく、英語の資料もある程度読める
- 税務やITよりも、会計に近い領域で力を発揮したい
また、受験時点でキャリア志向が明確でないけれど、数字で考えるのは好きな人にとっても、BARは良い選択肢になると思います。
BARって実際難しいの?合格率や感想の調査結果。

USCPAのDiscipline科目の中でも、BARは「中〜やや難しめ」のポジションと言われています。
①合格率の目安
2024年第4四半期(Q4)のNASBA公表データによると、BARの合格率は38.1%でした。
選択科目3つの中では最も低い数値であり、FAR(39.6%)と同程度の難易度と言えるでしょう。
以下はDiscipline(選択)科目の比較です。
- TCP(Tax Compliance and Planning):73.9%
- ISC(Information Systems and Controls):58.0%
- BAR(Business Analysis and Reporting):38.1%
この数字だけを見ると、BARは最もハードルが高そうに見えますが、実際には向き・不向きで感じ方が大きく変わることも多いです。
なので、一概に合格率の高い・低いだけで選択科目を決めるのは得策ではないこともあるのに注意が必要です。
合格率はたしかに低いものの、特に以下のようなタイプの方であればBARの得点力を伸ばしやすい傾向があるはず。
- FARやAUDで高得点が取れた/得意だった人
- 会計情報を分析・活用するような業務に興味がある人
- 資料読解(TBS)に抵抗がない人
合格率はあくまで全体傾向であり、自分の得意領域と重なるかどうかが合否を分ける大きなポイントです。
②受験生のリアルな声
そのほか、SNS・Redditなどから抜粋してみた受験生の方の感想をまとめました。
- 「FARに似てるけど、思ったより資料読みが多くて時間ギリギリだった」
- 「政府会計の比率は少ないけど、苦手だと足元をすくわれる」
- 「TBSが難しいというより、時間の管理がしんどい」
- 「英語での分析的読解が苦手だと、想像以上に疲れる」
- 「一番面白かった科目。FAR・AUDが好きな人は絶対こっち」
合格できた人の多くは、「本試験ではとにかく焦らないこと」「TBSで粘りすぎないこと」がポイントだったと述べています。
Q&A:BAR選択で迷う方へ

最後に、BARの選択で迷っている方に向けてQ&Aをまとめてみました。
Q1. BARとFARの違いは?
FARは「会計処理の理解と適用」が主軸、BARは「その財務情報を分析・活用する力」が問われます。
具体的には、FARでは仕訳や財務諸表の作成が中心だったのに対し、BARでは「この財務情報をどう使って意思決定するか」「開示要件をどう判断するか」など、応用的・分析的な問題が中心です。
Q2. BARの中で特に出やすいテーマは?
傾向としては以下のトピックが頻出です。
- CVP分析(損益分岐点分析)や意思決定会計
- セグメント情報・IFRS基準・収益認識・無形資産
- サステナビリティ報告・統合報告
なお、政府会計(Fund accounting)は出題比率は少なめですが油断禁物です。
Q3. 英語が苦手でもBARを選んで大丈夫?
BARはTBS問題の文量が多く、資料読解の負担が大きめです。
英語が苦手な方にとっては、REGやTCPよりも難しく感じる可能性があります。
ただし、時間をかけて慣れていけば十分に対応可能なので、早めの演習&復習をおすすめします。
迷ったら1ヶ月だけお気軽にコーチングを受講いただくのも検討してみてください。
なんでもご相談・お悩みをお伺いします!
Q4. 最終的な選び方のポイントは?
以下のような判断基準がおすすめです。
- 会計が得意、分析が好き:BAR
- 税法が得意、ルール暗記に強い:TCP
- ITやシステム、内部統制に強い:ISC
特にBARに関して言えば「FARが得意で、数字で考えるのが好きなタイプ」という方はBARにかなり向いていると考えられます。
まとめ:USCPAのBARはMC・TBSをバランスよく学習すれば必ず合格する!

以上、BARの特徴についてご紹介しました。
BARは単なる会計処理ではなく、数字をどう読みどう経営に活かすか?を問う実践的な科目です。
FARやAUDと親和性が高く、分析的な視点を持つ人にとってはむしろ楽しさを感じる科目ではないでしょうか。
一方で、出題範囲の広さや、資料読解・判断の重さもあって、戦略なしで突っ込むと時間切れや失点に繋がりやすい側面もあるため、自分の得意・不得意やキャリア志向と照らし合わせて、しっかり選ぶことが大切です。
USCPAはコストも時間もそれなりにかかる試験なので、今回の記事を読んでいただいた方が、是非1日でも早くUSCPA合格を勝ち取られることを願っています。


